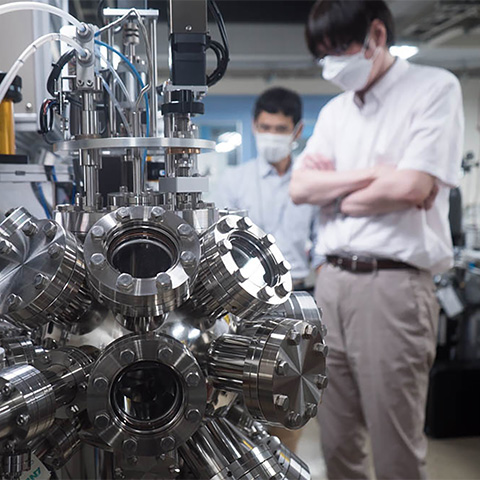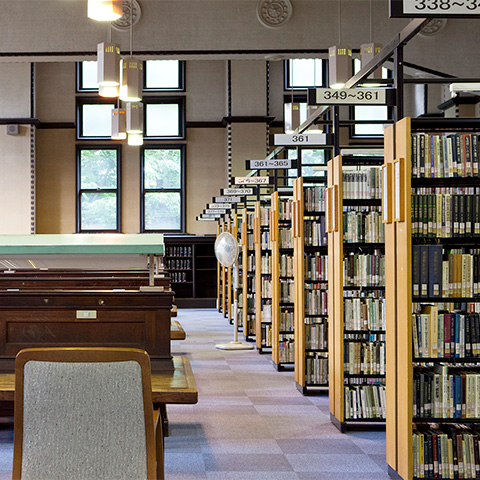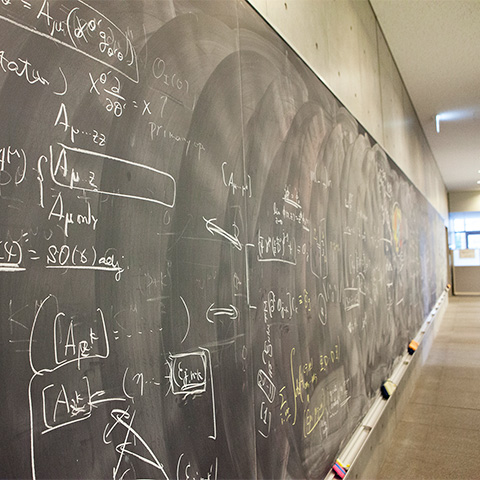化学教室の歩み
横にスクロールできます
| 年 | 東京大学・化学教室の出来事 | 主な政治・社会史、化学界の出来事 |
|---|---|---|
| 1797 | 幕府、昌平坂学問所を開講 | ドルトン(イギリス)が原子論を唱える(1803) |
| 1847 | 宇田川榕菴、我が国初の化学書「舎密開宗」の翻訳を完成 | |
| 1855 | 幕府、九段坂に洋学所を開設 | ペリー来航(1854) |
| 1856 | 幕府、洋学所を蕃書調所と改称 | |
| 1860 | 蕃書調所に精錬方(化学部門)ができる 幕府、下谷に種痘所を開設(東大医学部の発祥) |
桜田門外の変 |
| 1861 | 小川町に蕃書調所が移転、精錬方が実質的に発足(化学教室の発祥) | アメリカ南北戦争(1861-65) |
| 1862 | 蕃書調所、神田一ツ橋に移転、「洋書調所」と改称 | |
| 1865 | 精錬方を「化学所」と改称(「化学」という言葉が初めて公的に使用される) | ケクレ、ベンゼンの構造を発表 |
| 1867 | ハラタマ、初の外国人教師として開成所に着任 | 大政奉還 |
| 1869 | 昌平坂学問所を復興、昌平学校として開校 | メンデレーエフ、周期表を発表 |
| 1871 | 昌平学校廃止。工部省に工学寮設置 | 廃藩置県 |
| 1874 | アトキンソン来日、分析化学・応用化学を担当 | ファント・ホッフとル・ベル、炭素の正四面体説発表 |
| 1875 | 薬品精製所、化学実験所設立 | |
| 1877 | 工学寮を工部大学校と改称。東京大学発足。 久原躬弦、アトキンソンの下の助教授に就任 |
西南戦争 |
| 1878 | 駒場農学校開設 | 化学会(後の日本化学会)結成 |
| 1879 | 第1回学位授与式。久原躬弦、英国化学会誌に論文掲載(東京大学初) | |
| 1881 | 松井直吉、日本人初の教授に就任(有機化学)。櫻井錠二、講師に就任 | |
| 1882 | 櫻井錠二(24歳)、教授に昇任(物理化学) | |
| 1884 | 久原躬弦と高松豊吉、教授に就任 | |
| 1885 | 理学部、本郷へ移転。理学部より工学系の学科が独立 松井直吉・久原躬弦は工学系へ転出 |
伊藤博文、初代内閣総理大臣に就任 長井長義、エフェドリンを発見 |
| 1886 | 工部大学校を合併し、帝国大学設立。帝国大学理科大学化学科と呼称 ダイヴァース、帝国大学理科大学教師に転じる |
|
| 1888 | 第1回博士号授与(櫻井錠二ら) | |
| 1890 | 雑誌会開始(現在に至るまで続く、我が国最長の学術会合) | |
| 1893 | 櫻井が第一講座、ダイヴァースが第二講座教授に就任 | |
| 1894 | 櫻井、ベックマン法の改良による分子量測定法開発 | 日清戦争。北里柴三郎、ペスト菌を発見 |
| 1896 | 池田菊苗、助教授に就任 | |
| 1897 | 帝国大学、東京帝国大学へ改称 | J. J. トムソン、電子を発見 |
| 1899 | ダイヴァース帰国、名誉教授となる。垪和為昌、第二講座教授昇任 |
横にスクロールできます
| 年 | 東京大学・化学教室の出来事 | 主な政治・社会史、化学界の出来事 |
|---|---|---|
| 1900 | ダイヴァースの胸像建立 | 高峰譲吉、アドレナリンを発見 |
| 1901 | 化学第三講座新設、池田菊苗が教授に就任 | 第1回ノーベル賞、ファント・ホッフらに授与 |
| 1906 | 化学第四講座新設、松原行一が担当 | 日露戦争(1904~05) アインシュタイン、特殊相対性理論を発表 |
| 1907 | 日本化学会、櫻井賞牌制定(現・日本化学会賞) | 東北帝国大学設立 |
| 1908 | 池田菊苗、うまみ成分グルタミン酸Naを発見 | |
| 1909 | 松原行一、教授昇任 片山正夫、可逆電池の起電力がギブスの自由エネルギーに相当することを解明 |
鈴木梅太郎、ビタミンB1を発見(1910) |
| 1912 | 眞島利行、ウルシオールの構造決定 | |
| 1913 | 垪和為昌辞職。後任として柴田雄次が第二講座助教授に就任 | |
| 1914 | 柴田雄次、金属錯塩の分光学的研究 | 第一次世界大戦勃発 |
| 1915 | 化学科入学試験を初めて実施。 片山正夫、「化学本論」を発表。また表面張力の「片山式」提出 |
|
| 1916 | 化学科の建物完成(現在の化学東館) | 理化学研究所設立(1917) |
| 1918 | 松野吉松、錯イオンの原子価をゾルの凝結値より決定 | スペイン風邪が世界的流行(~1919) |
| 1919 | 東京帝国大学再編成、法・医・工・文・理・農・経済の各学部設立 東京帝国大学理科大学から東京帝国大学理学部へと名称変更 櫻井錠二退官、池田菊苗が第一講座担任に変更 片山正夫が東北帝国大学より転任、第二講座担当 柴田雄次が第三講座を担当、四教授体制となる 生物化学講座創設、医学部生化学教授柿内三郎が併任 |
ヴェルサイユ条約、第一次世界大戦終結 ラザフォード、α線による原子核破壊実験 |
| 1920 | 聴講生として女子の入学を認める | |
| 1921 | 4月始業となる 分析化学講座設立、山口輿平助教授就任 |
|
| 1922 | 柴田雄次が分析化学講座を担任 電気化学講座設立、山口輿平が担任 化学東館建物(第二期) |
ソビエト連邦成立 バンティングら、インスリンを発見 |
| 1923 | 化学東館竣工 池田菊苗退官、鮫島實三郎が第一講座教授に |
関東大震災 |
| 1924 | 左右田徳郎、生物化学講座助教授に就任 | 高橋克己、ビタミンAを結晶化 |
| 1925 | 安田講堂落成 水島三一郎、デバイの分子極性を電波分散により実証 |
治安維持法発布 ハイゼンベルク・ディラックらにより量子力学が誕生 |
| 1926 | Bull. Chem. Soc. Jpn. 創刊 柴田雄次「無機化学概要」発刊 |
シュレーディンガー、波動力学を発表 |
| 1927 | 水島三一郎、助教授就任 鮫島實三郎「物理化学実験法」刊行 真島利行ら「日本化学総覧」刊行 |
金融恐慌 ハイゼンベルク、不確定性原理を発表 |
| 1929 | 鮫島實三郎、固溶体生成理論を発表 | 世界恐慌 |
| 1933 | 明治期最後の教官であった松原行一退官、久保田勉之助が後任に。 木村健二郎教授昇任 水島三一郎、回転異性体の発見。ラマンスペクトルによる研究発表 |
5.15事件(1932) 中性子の発見(1932) 国際連盟脱退(1933) |
| 1934 | 理学部2号館新築 久保田勉之助、教授昇任 鮫島實三郎「膠質学」上巻を上梓 |
キュリー夫妻、人工放射能を発見 |
| 1935 | 鮫島實三郎「化学論」上梓 | |
| 1936 | 化学東館の渡り廊下完成 柴田雄次・柴田桂太「金属錯塩の接触作用」上梓 |
2.26事件 |
| 1937 | 鮫島實三郎「膠質学」下巻を上梓 | 日中戦争開戦 |
| 1938 | 片山正夫退官。水島三一郎、教授昇任。 | ハーンら、ウランの核分裂を発見 |
| 1939 | 左右田徳郎、教授に昇任 鮫島實三郎「物理化学実験法」上梓 |
第二次世界大戦始まる |
| 1940 | 柴田桂太ら、シトクロームCを発見 | |
| 1941 | 東京帝国大学報国隊を編成 大学の修業年限を3ヶ月短縮、徴兵検査の開始 |
太平洋戦争開始 |
| 1942 | 柴田雄次退官。木村健二郎、第三講座へ配置転換、南英一・山口輿平が教授昇任 水島三一郎・森野米三ら、回転異性体の一つ「ゴーシュ型」の存在確認 |
英ICI社、ポリエチレンの生産開始 ミッドウェイ海戦 |
| 1943 | 「東京帝国大学学術大観」全5冊刊行 | 学徒出陣開始 |
| 1944 | 帝国大学新聞休刊 | |
| 1945 | 輻射線化学研究所創設、水島三一郎が初代所長就任 貴重な図書・実験器具を福島県白河市へと疎開 合成化学講座総説、漆原義之が教授に昇任し担当 |
東京大空襲 広島・長崎に原爆投下 ポツダム宣言受諾、終戦 |
| 1946 | 久保田勉之助退官。 漆原義之が化学第四講座に配置転換、島村修が合成化学講座を担当 |
東京裁判 日本国憲法発布 |
| 1947 | 東京帝国大学を東京大学と改称、理学部化学科と改称 島村修、教授昇任 |
|
| 1948 | 山口輿平退官。森野米三、専任教授に就任 | トランジスタの発明 |
| 1949 | 東京大学(新制)設立。 | 湯川秀樹、ノーベル物理学賞受賞 |
横にスクロールできます
| 年 | 東京大学・化学教室の出来事 | 主な政治・社会史、化学界の出来事 |
|---|---|---|
| 1951 | 鮫島實三郎退任。赤松秀雄、化学第一講座の教授に昇任 | 対日講和条約調印 |
| 1953 | 新制東京大学大学院が発足 | ワトソン・クリックら、DNAの構造を解明 |
| 1954 | 左右田徳郎退任。赤堀四郎(阪大教授)、本学教授を兼任し、生物化学講座を担当。8講座のうち6講座が名称を変更 | ビキニ環礁にて第五福竜丸事件。本学科の木村教授が「死の灰」の分析を担当。赤松秀雄、有機半導体をNature誌に発表 |
| 1955 | 原子核研究所創設 | 神武景気(~1957) |
| 1956 | 木村健二郎退任。斎藤信房、無機化学講座の教授に昇任。 | |
| 1957 | 物性研究所創設(港区六本木) | |
| 1958 | 薬学部創設。生物化学講座の担任、赤堀四郎から江上不二夫へ | 東京タワー完成 |
| 1959 | 生物化学講座、化学科から生物化学科へと移行 水島三一郎退任、島内武彦が物理化学第一講座教授へ昇任 |
|
| 1960 | 南英一退任、藤原鎭男が分析化学講座教授へ昇任 | 日米安保条約改定、60年安保事件 |
| 1961 | 化学教室発祥100周年。化学新館着工 | |
| 1962 | 天然物有機化学講座創設、高橋武美が教授に昇任して担当 漆原義之退任、大木道則が教授に昇任して有機化学第一講座を担当 化学新館、寄付により完成 |
キューバ危機 |
| 1963 | 化学反応学講座新設、田丸謙二が教授に昇任して担当 無機合成化学講座新設、藤原鎭男が兼任 |
|
| 1964 | 物理有機化学講座新設 放射化学講座は原子力工学科の建物に設置され、浜口博が教授に昇任 |
東京オリンピック 東海道新幹線開通 |
| 1965 | 大学院改組、理・医・薬・工・農の5研究科を設置。化学科は理学研究科へ 大木道則、物理有機講座へ移動。稲本直樹が教授に昇任、有機化学第一講座担当。 |
朝永振一郎、ノーベル物理学賞受賞 |
| 1967 | 佐佐木行美、教授に昇任して無機合成化学講座を担当 | |
| 1968 | 東大紛争、安田講堂封鎖占拠 | 全国で大学紛争 |
| 1969 | 安田講堂攻防戦。入学試験が中止に 森野米三退任。朽津耕三、教授に昇任して物理化学第三講座を担当 |
|
| 1970 | 大阪万博 | |
| 1971 | 赤松秀雄退任。黒田晴雄、教授に昇任して物理化学第二講座を担当 | |
| 1973 | 島村修退任。向山光昭が有機化学第二講座を担当(東工大教授と併任) 向山アルドール反応の発見 |
江崎玲於奈、ノーベル物理学賞受賞 オイルショック |
| 1974 | 向山光昭、本学専任教授へ | |
| 1975 | 浜口博退官。斎藤信房、放射化学講座へ移動 不破敬一郎、教授に昇任して無機化学講座を担当 |
|
| 1976 | 分光化学センターを新設 | ロッキード事件 |
| 1977 | 島内武彦退任、田隅三生が物理化学第一講座教授に就任 斎藤信房退任、富永健が放射化学講座の教授に就任 |
|
| 1978 | 地殻化学実験室を新設 | |
| 1981 | 藤原鎭男が退任、増田彰正が神戸大より迎えられ、分析化学講座教授 | 福井謙一、ノーベル化学賞受賞 |
| 1982 | 化学西館完成 | |
| 1984 | 田丸謙二退任。岩澤康裕が助教授就任、化学反応学講座を担当 | |
| 1986 | 岩澤康裕、教授昇任。不破敬一郎退任、小間篤が無機化学講座教授に就任 | 国鉄分割民営化。ミュラーとベドノルツ、高温超伝導体の発見 |
| 1987 | 向山光昭退任。奈良坂紘一、有機化学第二講座教授の教授に昇任。高橋武美退任。岩村秀、分子研より迎えられて天然物有機化学講座教授就任。 | 利根川進、ノーベル医学生理学賞受賞 |
| 1988 | 大木道則退任。岩村秀、物理有機化学講座を併任。朽津耕三退任。近藤保、物理化学第三講座教授に昇任。 | リクルート事件 |
| 1989 | 稲本直樹退任。岡崎廉治、有機化学第一講座教授に昇任。佐佐木行美退任。齋藤太郎が大阪大学より迎えられ、無機合成化学講座教授に就任。 | 平成に改元。消費税導入。天安門事件。ベルリンの壁崩壊 |
| 1990 | 橘和夫、天然物有機化学講座担当教授に就任 | ドイツ再統一 |
| 1991 | 分光化学センター、スペクトル化学研究センターに転換 | 湾岸戦争。ソビエト連邦消滅。バブル景気終焉。 |
| 1992 | 増田彰正退任。梅澤喜夫、北海道大学より迎えられて分析化学講座教授に就任。黒田晴雄退任。太田俊明、広島大学より迎えられ、物理化学第二講座教授に就任。 | |
| 1993 | 大学院重点化に伴い、理学系研究科化学専攻となる。12講座の名称変更。 | 衆院選で自民党敗北、細川内閣成立。 |
| 1995 | 岩村秀退任。中村栄一、東工大より迎えられて物理有機化学講座教授に就任 | 阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件 |
| 1996 | 富永健退任。西原寛、慶応大学より迎えられて無機化学講座教授に就任 | |
| 1997 | 近藤保退任。山内薫、量子化学講座教授に就任。田隅三生退任。濵口宏夫、構造化学講座教授に就任 | 消費税5%へ。京都議定書採択。香港返還 |
| 1998 | 岡崎廉治退任。川島隆幸、有機ヘテロ原子化学講座教授に就任 | |
| 1999 | 齋藤太郎退任。塩谷光彦、生物無機化学講座教授に就任 |
横にスクロールできます
| 年 | 東京大学・化学教室の出来事 | 主な政治・社会史、化学界の出来事 |
|---|---|---|
| 2000 | 白川英樹、ノーベル化学賞受賞 | |
| 2001 | 米国同時多発テロ。野依良治、ノーベル化学賞受賞 | |
| 2002 | 21世紀COEプログラム「動的分子論に立脚したフロンティア基礎化学」(リーダー:岩澤康裕)が開始 | 田中耕一、ノーベル化学賞受賞 小柴昌俊、ノーベル物理学賞受賞 |
| 2003 | 小間篤退任。長谷川哲也、東工大より迎えられ固体化学講座教授に就任。 | |
| 2004 | 国立大学独立行政法人化 | スマトラ島沖地震 |
| 2006 | 太田俊明退任。大越慎一、本学工学系研究科より迎えられ、物性化学研究室教授に就任。 | |
| 2007 | 梅澤喜夫退任。小澤岳昌、分子研より迎えられ、分析化学研究室教授に就任。奈良坂紘一退任。 小林修、東大薬学部より迎えられ、有機合成化学研究室教授に就任。グローバルCOEプログラム「理工連携による化学イノベーション」(リーダー:中村栄一)開始 |
山中伸弥、iPS細胞作成に成功 |
| 2008 | 岩澤康裕退任。 | リーマンショック。南部陽一郎・小林誠・益川敏英、ノーベル物理学賞を受賞。下村脩、ノーベル化学賞を受賞 |
| 2009 | 衆院選にて民主党が勝利、鳩山内閣発足 | |
| 2010 | 川島隆幸退任。菅裕明、東大先端研より迎えられ、生物有機化学研究室教授に就任。 | 小惑星探査機「はやぶさ」帰還。鈴木章・根岸英一、ノーベル化学賞受賞。 |
| 2011 | 化学教室発祥150周年記念式典を挙行。リーデイング大学院プログラム「フォトンサイエンス・リーデイング大学院(ALPS)」開始。 佃達哉、北海道大より迎えられ、化学反応学研究室教授に就任。 |
東日本大震災。福島第一原発事故 |
| 2012 | 濵口宏夫退任。合田圭介、UCLAより迎えられ、構造化学研究室教授に就任。リーデイング大学院プログラム「統合物質科学リーダー養成プログラム(MERIT)」開始。 | 山中伸弥、ノーベル生理学・医学賞を受賞。衆院選にて自民党が勝利、安倍内閣発足。 |
| 2013 | 化学西館改修工事 | |
| 2014 | 中村栄一、特別教授に就任。化学西館改修工事完了。Global Science Course (GSC)開始 | 消費税8%へ。赤崎勇、天野浩、中村修二、ノーベル物理学賞を受賞。 |
| 2015 | 橘和夫退任。 | 梶田隆章、ノーベル物理学賞を受賞。 |
| 2016 | 中村栄一退任。革新分子技術総括寄付講座設立。 磯部寛之、東北大より迎えられ、物理有機化学研究室教授に就任。Global Science Graduate Course (GSGC)開始 |
大隅良典、ノーベル生理学・医学賞を受賞。 |
| 2018 | Robert Campbell アルバータ大より迎えられ、生命有機化学研究室教授に就任。 | 本庶佑、ノーベル生理学・医学賞を受賞。 |
| 2019 | 国際卓越大学院 WINGS 開始 | 令和に改元。消費税10%へ。 |
| 2020 | 西原寛退任。大栗博毅、東京農工大学より迎えられ、天然物化学研究室教授に就任。山田鉄兵、九州大学より迎えられ、無機化学研究室教授に就任。オンライン講義。 | 新型コロナウイルス感染症の蔓延による緊急事態宣言発令。菅内閣発足。 |
| 2021 | グリーングリーントランスフォーメーションを先導する高度人材育成(SPRNG GX)開始 | 東京オリンピック開催。眞鍋淑郞ノーベル物理学賞受賞。岸田内閣発足。 |
| 2022 | 長谷川哲也退任。一杉太郎、東京工業大学より迎えられ、固体化学研究室教授に就任。 | |
| 2023 | 山内薫退任。 | 新型コロナ「5類」へ移行 |
| 2024 | 塩谷光彦退任。楊井伸浩、九州大学より迎えられ、機能無機化学研究室教授に就任。石﨑章仁、分子研より迎えられ、量子化学研究室教授に就任。学部講義「情報化学」開講 | 石破内閣発足。新紙幣発行。 |
| 2025 | 小林修退任。「グリーン物質変換」総括寄附講座設立。雑誌会2000回記念。 |